水のきらめき - 記事一覧
https://www.tsunabuchi.com/waterinspiration/
| 発行日時 | 見出し |
|---|---|
| 2025/10/22 21:12 |
桂民海ってどなた?


日本ペンクラブのサイトのトップに以下の声明文が掲載された。
桂民海(Gui Minhai、グイ ミンハイ)というかたを僕は知りませんでした。スウェーデンの国籍を得たのにタイに行った時に中国に拉致されるって恐ろしいですね。 これを読んで思い出したことがあります。 大学生の頃、学内に中国からの留学生が何名かいたのですが、いつも中国人だけでかたまっていて、話しかけられない雰囲気でした。当時は一般の中国人は海外に渡航できず、留学できた人はみんな共産党高官の子息だと言われていました。 そんなとき、中国が海外からの旅行者を受け入れるようになりました。そうなった二年目に中国を旅行しました。日本でビザを取ると高いというので、まずはまだ英国領だった香港に行き、そこで日本で取るよりは安いというビザを取り、列車で広州に入りました。 その後、桂林、西安、上海と回りました。どこに行っても一般民衆は優しかったのを覚えています。「日本から来た」というと歓迎してくれて、いろいろ英語で話して、人によっては「もう二度と会えない」といって泣いた人もいました。当時一般の中国人は海外へは渡航できないのでした。 日本に留学していた学生の態度と、中国にいた一般民衆の態度の差がなぜなのかがよくわかりませんでした。きっと共産党高官の子息だから、いつか日本を追い越すために、日本の学生を敵視しているのかなと噂しましたが、本当のことはわかりません。 今では中国人はお金さえあれば日本に自由にやってくるようになりました。当時中国で会った人も何人かはきっと来たでしょう。いい時代になったと思いました。でも、それでいろいろと問題が生まれているようです。 中国から日本に留学する際は、必ず家族を中国国内に住まわせ、中国を裏切るような行為ができないようにしているというのです。もし共産党の批判などしたら、家族がどんな目に合うかわからないとか。単なる噂であってほしいと思いますが、「中国人が日本に留学して共産党を批判するとどうなるのか」とAIに聞くと、以下の返答が得られました。
これを読んで、大学にいた留学生たちはお互いに監視し合って、日本人と仲良くできなかったのかなと思いました。 国の決めた規則に従わないとならない中国人は大変だなと思います。きっと理不尽な規則がなければ、もっと仲良くできたでしょう。特に問題なのは国防動員法でしょう。そんな規則があったら、有事の際に日本人は国内にいる中国人を警戒せざるを得ない。悲しいことです。 自国の政府を批判できるというのは、ありがたい。 |
| 2025/10/19 23:46 |
演劇とヌースフィア


劇団Prayers Studio の渡部朋彦さんと、演劇とヌースフィアについて対談しました。少し長いので、何回かに分かれています。 ご覧ください。 |
| 2025/1/27 23:15 |
マスク氏の訴訟は何を意味しているのか


バイデン政権はその末期にmRNAインフルエンザワクチンの開発のため、モデルナ社に5億9000万ドルを交付したが、トランプ政権はその二日後、5000億ドルという巨費をmRNA研究もおこなうスターゲイトという民間プロジェクトに投じると発表した。それについてマスク氏は「企業には約束したインフラ投資を裏付ける資金が実際にはない」とXに書いた。 これを捉えて日本のマスメディアでは「マスク氏とトランプ氏は対立している」という論調が見られたが、重要な問題はそこではない。 スターゲイトにはOpenAI の CEO サム・アルトマン氏が参加している。かつてOpenAIはマスク氏も参加していたが、OpenAI の方針転換によって、マスク氏はOpenAI とサム・アルトマン氏などを訴えることにした。その訴訟についての詳細はこちらにある。 訴訟の内容を簡単にまとめると、マスク氏はOpenAI の設立当初の合意を破棄されたことで訴訟を起こした。 OpenAI 社は人類にとって安全で有益な汎用人工知能AGI(Artificial General Intelligence)を開発することを目的とし、原告マスク氏とアルトマン氏等との間の合意の元に設立された非営利団体だった。マスク氏はOpen AI 社の設立当初から、多額の資金の拠出に加えて有能な人材の確保にあたって重要な役割を果たす等、多大な資源を割いたにもかかわらず、アルトマン氏は 2019 年に Open AI 社の CEO に就任すると、営利を目的とする子会社(Subsidiary)を設立し、2020 年 9 月 22 日にはマイクロソフト社との間で同社に対して独占的に 但し、マイクロ ソフト社へのライセンスは Open AI の AGI 以前の技術にのみ適用され、AGI に関するいかなる権利も取得していないとのことであり、OpenAI がいつ AGI に到達したかを決定するのは、マイクロソフトではなく、OpenAI, Inc.の非営利理事会とのことだそうだ。 これらを受けて、マスク氏は OpenAI 社とアルトマン氏らを契約違反、禁反言、信任義務(Fiduciary Duty)違反、不公正な事業慣行(Unfair Business Practices)等で訴訟を提起した。 ちょっとややっこしい話です。汎用人工知能AGI(Artificial General Intelligence)とはどのようなAIを指すのかがはっきり書かれていません。さらに「Generative Pre-Trained Transformer (GPT)-3 言語モデル のライセンスを供与する」と書かれていますが、AIは進化します。育っていくと言ってもいいでしょう。だからGTP-3のライセンスを与えたとしても、使用している間に情報を揃え、AGIに至る可能性があります。このことが普通の商品とは違って、このAIの訴訟を複雑にしています。しかも、動物のように育った時の姿がAIだと明確ではありません。子牛を育てたら大人の牛になるから将来についてある程度予測できますが、AIはこれからどのレベルまで育つかわからない。人間が介入して操作できるレベルならまだいいのですが、AIが自律的に思考を始めたりしたらどのような状態になるのか予想がつきません。だからこそ、安全で有益な汎用人工知能AGIを開発するための非営利団体を作り、あらゆるレベルのチェックができるようにオープンソースにしたのです。それを私企業が独占時に使えるようになってしまったら、何が起こるのか想像を超えていくでしょう。 多くの人にとってはこの話は少し大袈裟だと思うかもしれませんが、そんなことはありません。これは複製子の話なのです。 生命には必ず遺伝子という複製子があります。遺伝子は複製(コピー)されていきます。だからそれを複製子ともいう。遺伝子は複製子の一形態です。遺伝子は環境との関係で進化し、いろんな形態の生命を産みだしました。 生命は最初、たった一つだけ生まれたと考えられています。それがいろんな環境や条件によって分化し、進化した。その結果、現在の地球上に何百万という多種の生物を生み出した。絶滅した生物も加えるときっと何十億、何百億の種類があったのでしょう。同時に遺伝子も細分化していきました。できた生命のうちの一種類が人間です。 人間は遺伝子とは別のレベルの複製子を作りました。それが言語です。言語のおかげで人間はどんな動物よりも有利に生きていくことができるようになりました。言語を持つことによって複雑な思考を可能にしました。さらにしばらくすると、文字を生み出すことで時間や場所を超越して、普通に考えるよりより複雑な思考を組み立てるようになります。もし文字がなかったら電磁気学や化学など、多くの学問体系は伝達できなかったでしょう。 複製子はその誕生の際に謎が生まれます。なぜその複製子が生まれたのか、誰も説明ができない。遺伝子がなぜ生まれたのか、様々な説はありますが、どの説が正しいかは特定されていません。言語も同様です。 僕たちは言葉を普段簡単に使っていますが、それがどうやってできたのか、誰も知りません。遺伝子と同じで説はたくさんあるようです。しかし、確定的な誕生の秘密は解き明かせていません。 どんな生物も遺伝子の存在を知りませんでした。人間もかなり長い間知らなかったのですが、言語という複製子を得ることで、次第にその存在を認知し、その理解を広げているところです。生物が遺伝子の存在を知らなかったように、人間は言葉という複製子の由来も役割も完全には把握していないのです。それがさらに上位の複製子、つまりAIが誕生することで、AIにとっては理解できるようになるのかもしれません。AIがもし仮に理解できるようになったとしても、人間にその内容が理解できるかどうかは未知です。おそらく大量のデータによって区別される内容なので、人間の脳の容量では理解できないかもしれない。だから、人間の知力ではAIに置いてけぼりにされてしまいます。もし充分に進化したAIと人間が知力で競争しなければならなくなったらどうなると思いますか? 人間の惨敗ですね。ここに大きな問題があるのです。 複製子は誕生してから時間の経過とともに進化していきます。生命の場合は遺伝子の進化とともに複雑な生命が生まれ、地球環境を変化させ、安定的に存在できる状況を生み出していきました。その結果人間が生まれ、人間はまた言語という複製子を生み出します。 生命が生まれたとき、その生命は酸素を吸う今のような生命はいませんでした。嫌気性菌という酸素を吸わない生物が最初生まれた。その多くは酸素に触れると死んでしまいました。ところが、その生物(菌)はその毒である酸素を排出しました。するとその生物が増えれは増えるほど毒である酸素が増えていきます。次第に酸素があっても生きていける生物ができ、ついには酸素を吸う生物(好気性生物)が出来てきます。つまり、最初の生物ができたとき、地球の環境に沿った生物が生まれ、次第に変化していきました。同じことが言語にもあったであろうことが推察されます。 最初に言葉を使い始めた人間はきっと簡単に使える言葉を使ったでしょう。しかも、そのときにあったものや存在した動きを表現したはずです。その多くは自然物とその動きだったでしょう。時間が経つにつれて、少しずつ複雑な概念を持つようになっていったと思われます。つまり複製子が生まれるとき、すでにそこに存在する何ものかを組み合わせて作ったはずです。 一度複製子が生れると、その内容が繰り返されます。繰り返されることで新たな何ものかが生まれてくる。 遺伝子の場合で言えば、単細胞生物がしだいに複雑化して、多細胞生物になり、雌雄化し、感覚器官を持つようになって、環境と深く関わるようになっていく。 言語の場合で言えば、自然物の描写から始まり、区別が複雑化精細化して、言葉がないかぎり生まれないような道具や規則や社会を生み出してきました。 AIも同様に、人間の間に生まれたら、最初は人間的な表現に終始するでしょうけど、独自の進化を始めることで人間は阻害されていく可能性が生まれます。特に人間社会が競争原理によって支配されていたら、AIが最初に学ぶことが競争原理になることは明確です。一企業のために作られた不完全なAIが、いつか自立した複製子となり完成したAIとなったとき、そのAIは一企業が有利に経営されるようにどんなことをはじめるのかきっと今の人類の想像を超えてくるでしょう。だとすると、それを止められる存在は、そのときにはないかもしれません。そうなると、いったいどんなことが起きるのでしょう? 人類にとって安全で有益な汎用人工知能AGIを開発することを目的とし、設立された非営利団体がオープンソースでおこなうのであれば、まだその危険性が回避されるかもしれません。だからこの訴訟は、単にマスク氏とアルトマン氏の利益の奪い合いだけの話ではないのです。 自立型AIが何を始めるのかは、人類の想像を超えることになるでしょう。それを生み出すことについて僕たちはどんなに慎重になってもなり過ぎることはないのです。 |
| 2025/1/27 14:42 |
2025年の日本


ざっと日本を見まわした印象を書く。僕の視点はとても狭いものだから、必ずしも正しくはないとは思うけど、僕という視点からの印象だ。 日本人の多くが、平和とは何かについて目を覚ます。 これは事実ではなく、推測であり僕の思いでもある。 縄文時代は一万年から一万五千年ほど、平和な時代が続いたと考えられている。なぜそのような時代が続いたのか、その理由はまだよくわからない。ただ、傷つけられた人骨が見つからないために、「おそらく戦いや争いのない時代だったのだろう」と考えられている。 弥生時代から古墳時代にかけて、日本でも争うようになってきた。大陸から人が入ってきたからかもしれない。大化の改新の頃には天皇の一族が殺し合っていたことがはっきりと歴史書に残っている。 大化の改新以降、日本に長い平和はなかなか訪れない。ギクシャクしながら戦国時代を迎え、争いが激しくなったことで、ついに平定されて江戸時代になる。元禄の頃の江戸は世界一の都市だったという。なぜそれが可能だったのか? いろんな理由が考えられると思うが、第一に日本人の民度が高かったから。そして、それはなぜ成し遂げられたのか? それが大事だ。 一つにはよく教育水術の高さが言われる。確かに識字率が高かった。では、なぜ識字率が高かったのか? それは将軍や領主など、上に立つものが下々が知恵を持つことを遮らなかったことが大きいのだろう。 古墳時代から大化の頃まで、大陸の人たちが来るようになって争いが増えた。それがやっと江戸時代で収まる。幕末になるとアメリカの来航をきっかけに欧米諸国が来るようになり、貿易を強制してきた。欧米は植民地化を考えていたようだが、そうはならなかった。そうはならずに第二次世界大戦の敗戦を迎える。損して得とれ。敗戦という損をして、平和な時代を勝ち取った。多くの植民地が戦後独立していった。 古墳時代の頃に大陸から人が来て江戸の平和を構築するのに千年と少しかかった。幕末から第二次大戦後の平和までは百年弱だった。今回海外からの人たちが流入していろんな混乱が生まれているようだが、次の平和を作り上げるまでには十年前後かかるのではないか? 日本人が目覚めるとそんなふうになるような気がする。 |
| 2024/9/22 9:57 |
「The Cripple of Inishmaan」を観て


Prayers Studio が主催で公演している「The Cripple of Inishmaan」を観てきた。 なぜ僕がこの芝居を見たいと思ったかというと、脚本がマーティン・マクドナーだったから。 マーティン・マクドナーがどういう人かを知っているのはなかなかの演劇通だと思う。僕は演劇通などではなく、たまたまある映画で知って印象に残っていた。その映画は「イニシェリン島の精霊」。アイルランドにアラン諸島と呼ばれる三つの島がある。イニシェモア島、イニシュマーン島、イニシィア島という。日本でも有名なアランセーターは、ここが発祥だ。その映画を見たとき、強く心を掴まれた。だから今回、Prayers Studio が「The Cripple of Inishmaan」をやると聞いたとき、ぜひ観てみたいと思った。 なぜそのように強く思うのか。その理由は僕の魂に深く刻まれていて、長い話になってしまうので、ここではその話はしないでおく。 まず、「The Cripple of Inishmaan」というタイトルを和訳してないのがクスッと思う。和訳したら、内容を誤解されて下手をしたら騒ぎになるだろう。 芝居って、演じられている内容が、見ている人によって違うものであることがある。マーティン・マクドナーはそのことがテーマの人だと思う。まあ、僕しかそうだと思わないかもしれないけど。たくさんの見方があるから。僕がそう思うのはもちろん「イニシェリン島の精霊」という映画を見たからではあるが、それ以外にも彼がアイルランド出身の両親からロンドンで生まれたということもきっと関係している。 そんな複雑な芝居を(まだどう複雑かは書いてないので多くの人には謎だと思うが、このあとに書いて行く) The Prayers Studio が演じるのだ。観ないわけにはいかない。 Prayers Studio は、稀有な演劇集団だ。劇団といえば、どうやって人を集めて多くの人に見てもらえるかを追求するものだが、彼らの追求の矛先は少し違う。彼らのは矛先は「いかに本物の芝居をするか」だ。6年ほど前、彼らのワークショップに参加させてもらった。その時の体験をここに書いた。 だから彼らの使う劇場はとても小さい。ほぼ目の前で演技をする。すると、彼らの細かい動作も、手の震えも、声の震えも、感情も、客席に丸わかりになる。だから俳優は、自分の気持ちを誤魔化すことができない。それをすると観客は容易に読み取ってしまう。自分の気持ちと向き合った芝居をされると、観客は芝居に深い没入を味わうことになる。大舞台でドタバタやる演劇とはまったく違う、アップの繊細な感情表現のシーンが多い映画のように精緻な芝居になる。 ここからは芝居の話をする。多少のネタバレがあるので、何も知らずに芝居に向かい合いたい人は、この先は読まないほうがいいだろう。 「The Cripple of Inishmaan」は、舞台がアイルランドのアラン三島の一つ、イニシュマーン島。その三島ではイニシュモア島が一番大きく、イニシュマーンは二番目の島だ。その島にある小さなよろず屋が舞台。小さな島だから、物資はあまり入ってこない。昔日本にもあったようなよろず屋を二人の女性が取り仕切っている。今の若い人にはよろず屋と言っても意味がわからないかもしれないが、僕の幼い頃には近所に一軒あった。食べ物や文房具や靴やいろんなものを売っている店だった。その看板には「藤田屋、ないものはない」と書かれていた。現代でそれを効率的、おしゃれにしたのが、コンビニだ。そこで少し年配と思われる女性が二人、愚痴を言い合っているシーンから始まる。 このシーンでいきなり持たされる謎は、「なぜこの二人の女性はつまらないことでビリーをああも罵るのか」。それが芝居の経過とともに明らかにされていく。 イニシュモア島は少しは観光化されていて、まあまあ人のいる場所になったが、それでも滅多に人に会うことはない。土がなく、岩ばかりで、そこで農耕をしたい人は海から海藻を運んできて岩の上に撒き、腐らせて土を作るところからしなければならなかった。1990年代の末にイニシュモア島に行ったが、その時でも風で土が吹き飛ばされてしまうので、年に何度か海藻を撒いていると聞いた。荒地に傾いた電柱が何本も立っていて、たるんだ電線が渡されていたのが印象に残っている。それがイニシュマーン島になるとどれほどの人に会えるのか? その雰囲気がセリフの中に巧みに織り込まれていた。 見ているのは、よろず屋の狭い部屋だけなのだが、そこで交わされるセリフに広大な荒地にほとんど人と会うことのない雰囲気が埋め込まれていた。凡庸な俳優がそんなセリフを言ったところで「あっそう」としか思えない些細なセリフが、荒地のことなど何も言ってないのに俳優の言葉から立ちのぼる。 やがて登場する「Cripple」なビリーが「アラン諸島を舞台にする映画」に出演しようとイニシュモア島に渡るのだが、そのことによって、なぜビリーが「Cripple」なのか。なぜ愛情深い二人のおばさんが、ああもビリーを罵るのか、そもそもこのイニシュマーン島がどういう場所なのかを浮き上がらせていく。 舞台に登場する「アラン諸島を舞台にする映画」は、実際にあるもので、その一部と思われる映像が芝居の中で披露される。その映画を村人たちが見ることで、一体何が起きてくるのか。人間の不思議さを多面的に見せてくれるいい芝居でした。 |
| 2024/9/16 18:36 |
「将軍」がエミー賞18部門で受賞


「将軍」というネットドラマがエミー賞の18部門で受賞した。最多22部門、25ノミネートを果たしていたが、そのうちの18部門で受賞したそうだ。今わかっている範囲でいうと、ドラマ部門作品賞、ドラマ部門主演男優賞・真田広之、ドラマ部門主演女優賞・アンナ・サワイだそうだ。他の15部門も知りたい。 「将軍」は1975年に小説化され、1980年に日本語訳が完成した。同時に、NBCによってテレビドラマとしても放送された。リチャード・チェンバレン、三船敏郎、島田陽子、などが主演していた。そのドラマを短縮して、日本ではまずは映画として公開された。父が和訳本の監修をしていたので、一緒にその映画の試写会を見にいった。 当時は浪人生か大学生かくらいの年だったが、あまりいい印象はなかった。九時間のドラマシリーズを二時間程度にまとめたのだから、仕方なかったかもしれない。でも、日本人としての文化的違和感があったように覚えている。 今回の新しい「将軍」を全て見てみた。見事に日本人が感じるであろう違和感を訂正していたように思う。きっとその違和感をスタッフが総出でぬぐいさっていったのだろう。今回の「将軍」はそういう意味で見事だと感じた。 残念ながら1980年のドラマ版は見てないので正確にはいえないが、当時のアメリカ人が思う日本人でドラマが作られていたと思う。例えば愛の告白では、日本人ならああいう告白はしないなと思ったが、今回のドラマでは修正されていた。 素晴らしい作品に仕上げたスタッフの皆さんに拍手を贈りたい。しかも、それで欧米の人たちをも納得させるのだから、日本の文化的背景についてかなり理解してもらえるようになったと言えるだろう。 1980年はバブル真っ只中、表面的な日本人観が世界を覆っていたのが、いろんな人の努力できちんと理解されるようになって来たということか。 |
| 2024/8/28 17:35 |
青山繁晴氏の告発


長らく体調を崩していたが、そろそろ復帰しないとこのまま引退なんてことになりかねないのでリハビリを始めた。 そのために複眼ニュースというサイトを作った。「はじめに」というページにこう書いた。
最近のマスメディアは伝えることが狭くなってきているように思う。例えば、ロシアのウクライナ侵攻にしても、以前からロシアはウクライナがNATOの基地を作るようなことがあったらそれを阻止します、というようなことを表明していたにもかかわらず、ウクライナはそれをしようとした。その結果の攻撃。ところがその経緯はほとんど触れられない。 似たことが今度は自民党内で起きた。以前から参議院議員の青山繁晴氏は、自民党にとって痛いことを言ってきた。二ヶ月前にもこんなことを言っていた。 だからかどうか、真実は闇の中だが、総裁選に立候補すると言っているのに、マスメディアには出してもらえなかった。陰湿ないじめに近い。ついに青山さんは記者会見を開いた。そのことについて新聞は触れたが、話した内容の肝心なところには触れなかったり、内容を軽くしていた。 青山氏は別の総裁選候補とは違う別の選択肢を提示したいと言って、二点を挙げた。 1.私が日本国の宰相になれば、まず最初に消費減税をおこなう。財務省は当然反対すると思うが、真正面から対峙して実現していく。これまでに報道されている11人の中で、 財務省と対峙して減税を行うと表明されてる方はいない。 増税や社会保険料の引き上げが政策に含まれていた岸田政権と違って、減税に転じるという選択肢を与える。 2.私は国会議員となって8年だが、 どなたからの支援もいただいていない。これからもいただくことはない。そもそも派閥グループに一切属していない。支援団体は全部お断りだ。つまり、業界団体であろうが宗教団体であろうが、 一切お断りしている。こういう候補者は、今の11人の方の中にいない。これが2つ目の選択肢であり、全ての議員にそうしろとは言わないが、モデルケースの一つにはなるだろう。 さらになぜ自民党総裁戦に出るのかというと、自民党の体質を変えるという。 自民党での党員集めは三年連続で一位だった。 さらに青山氏はこうも言った。 これで三年間党員を集め続けられたということは、自民党が真の国民政党に脱皮できるきっかけになりうると思うという。 このような考えをきちんと示す人を総裁候補として無視するのは、きっと膿となっている人なんだろうなと思わざるを得ない。 これからの総裁選の行方が楽しみだ。 以下は総裁選出馬の記者会見。 9月15日加筆 告示日に推薦人が15名しか集められなかったために、青山氏は総裁選に立候補できませんでした。立候補して他の候補者と論争できれば良かったのですが。 |
| 2024/7/28 4:34 |
宮田選手は五輪に出場すべきか?


体操女子・パリ五輪代表の宮田笙子選手(19)が「喫煙と飲酒行為が発覚した」ため代表を辞退したという報道に、あまり興味は持てなかった。僕は宮田さんをまったく知らないし、体操に格別の思い入れもなかったから。 でも、このデイリー新潮の記事を読んで、違うなと思った。何が「違うな」と思ったかを書く。 そうそうたる有名人が「宮田笙子は五輪に出場すべき」とXに投稿してもネット世論は完全無視 謎を解くカギはビートきよしの投稿にあった この記事の最後に、結論のようにこのように書かれている。
確かにネット民の中にはうさを晴らすために「宮田選手の件だけは正義が実現した」と思う人もいたかもしれないけど、多くは違うのではないかと思う。 あの記事を読んでいただくとわかるのですが、宮田選手がどう感じているのかがほとんど何も書かれていません。その裁断が降りたとき、「宮田選手はそれでも日本体操チームを応援している」というような記事をどこかで読みました。それは、僕も本当かどうかはわかりませんが、本当だとしたら、尊重してあげるべきでしょう。 有名人がいくら「あの程度なら許してやるべき」と言ったとしても、本人が「確かに悪いことをしました。代表から降ります」というなら、降ろしてあげるべきだと。 何度も言いますが、本当のことを僕は知りません。宮田選手がどう思っているかも、日本体操協会がどうしてそのような裁定を下したのかも。でも、宮田選手が日本人の美学をきちんと備えている選手だとしたら、「代表から降ります」と言っても不思議ではないし、本人がそれを望むなら、そのようにしたほうがいいのだと思います。 宮田選手は、「日本代表選手になる重み」を知っているのだろうと思います。 どんなに人生を賭けて努力してきたとしても、「私は代表選手に相応しくないことをしていた」と思っているなら、それを尊重すべきだと思います。 宮田選手はまだ19歳だと聞きます。きちんと彼女自身が果たしたい禊ぎを果たして、四年後のオリンピックに出場してもらいたいと思います。そのときはじめて、日本の代表として花開くのではないかと思います。 日本人として、「最高の選手たちに出場してもらい、オリンピックで勝ってほしい」という気持ちはわかります。でも、宮田選手ご本人が「日本を代表する最高の選手とはどのような存在か」を具現化する場所としてオリンピックを見ているなら、そのようにしてあげるのが本人のためだと思います。 |
| 2023/10/12 23:01 |
映画「福田村事件」


映画「福田村事件」が予想外のロングランになり公開劇場数を伸ばしている。この映画の何が面白いのか。きっとそれは誰に聞いてもうまく答えられないのではないか、と思う。なぜなら、森達也という監督が、「うまく答えられないこと」を撮ろうとしているから。言葉というレッテルでは表現しきれないこと。それを撮ろうとしているから。 そもそも森達也監督は監督デビューが「A」という映画だった。オウム真理教がテロを起こし、日本中が大騒ぎになっているその最中、オウム真理教の内側に入り、その日常を撮っていった。その映像に多くの人が驚いた。そして言葉を失った。 「あの凶悪集団が、、、」 「、、、」ではいろんなことが言えるかもしれないが、映画を見るとあの時代の雰囲気ではいいにくいことが見えてきた。そして、それに気づいた人は一人取り残される。 「言いたいが、言ったらどうなるのだろう?」 言い出すことに勇気が必要な何か。日本を覆い尽くしている言語化できない雰囲気に気づかされてしまう。そしてそれに気づくと誰にでも気軽には言えないので一人取り残される。よほど仲が良い、何を言っても許し合える人たちとしか言い合えない「あれ」。 映画「福田村事件」では、関東大震災当時言えなかったであろうことを令和の今、感じさせてもらう。なぜそれが言えなかったのか? 令和の今なら当たり前に言えるようになってきた。でも、と思考が止まる。 令和の今、言えないことがある。 それは注射のことであったり、安倍元首相の暗殺の真相であったり、ウクライナとロシアの背景であったり、海洋放出のことであったり、色々だ。でも、それらは言おうと思えば言える。書ける。恐怖心さえ乗り越えられれば。 「A」でも、「Fake」でも、「i-新聞記者ドキュメント-」でも、森監督は現在に生きている人には見えない、言えない、書けない何かを表現してきた。 映画「福田村事件」の舞台となった当時、そこに生きていた人たちはきっと気づいていなかったであろうセリフが出てくる。もし、映画「福田村事件」をこれから見ようとしている人は、ここから先は読まないほうがいい。そのセリフが出てきた時、僕は泣いてしまった。 関東大震災当時の日本人が言えなかったこと。もしかしたら、思いもしなかったこと。それは「鮮人なら殺してええんか」。 令和の今なら当たり前のことだ。どこの国の人だろうが、殺してはならない。だけど、関東大震災から五日後の、あの映画の舞台となった村では、「鮮人なら殺してええ」となってしまった。それがなぜか、その雰囲気がどうして出来上がっていったのか、それを丁寧に見せられる。 令和の今、積み重なってきた言えないこと。そういうものがあり、いつかにっちもさっちも行かなくなるかもしれないことに目が覚める。群れることで考えなくなるおぞましさ。上の言うことを疑うことなくまにうける恐ろしさ。自分が正しいと思ったら、感情的になる幼さ。 殺戮がおこなわれたあとで、水道橋博士が演じていた在郷軍人会分会長・長谷川の叫び声が耳から離れない。 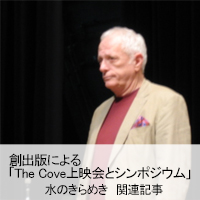 |
| 2023/8/24 17:53 |
(海洋放出以外の)代替案はあるが、公の場で検討されてこなかった


8時間ほど前に公開された国際環境NGO FoE Japan 満田夏花氏による汚染処理水についてのレポート。 とても重要だと思うので、ご覧ください。 |